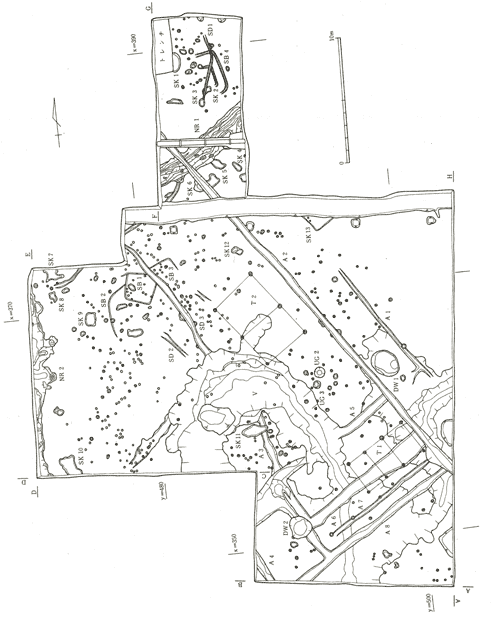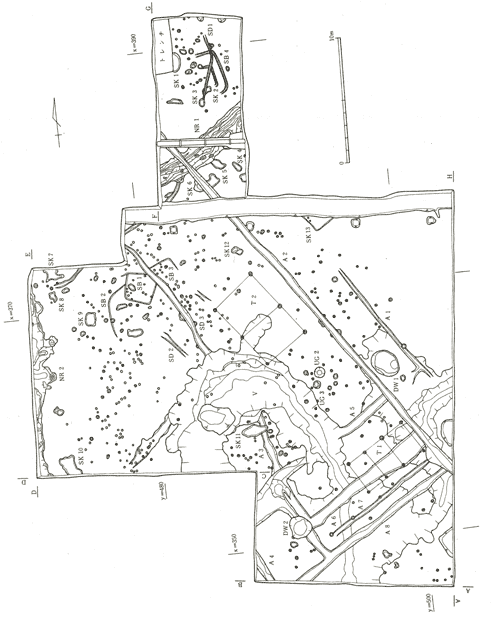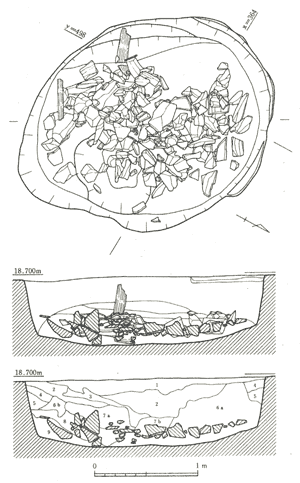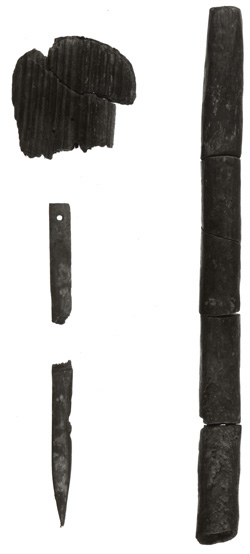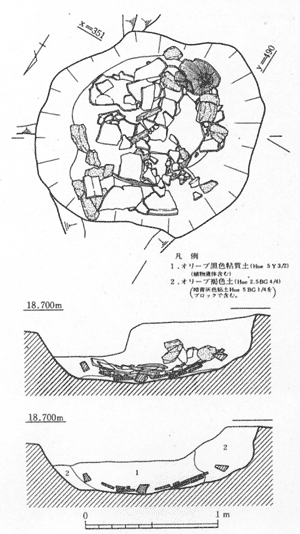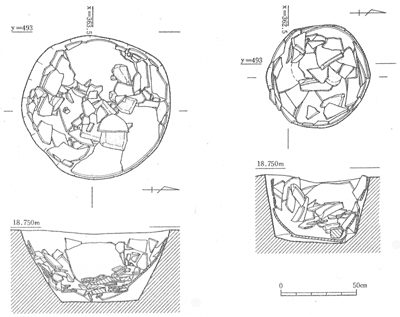この調査区では、弥生時代以降の様々な時期の遺構が検出されています(右図参照)。その中でも、吉田構内における江戸時代の集落構造が確認できたことが最も重要な成果と言えるでしょう。
江戸時代の遺構としては、井戸2基、埋甕3基(1基は試掘段階で検出されたため詳細は不明)があります。この他にも、遺物は出土していませんが掘立柱建物2基が検出されています。井戸や埋甕との配置関係から、同じ時期に建てられていたものと考えられます。
この遺構面の上に堆積する土層内からは17世紀の遺物が出土するため、これらの遺構は17世紀前半に形成され、短期間に廃絶したのでしょう。
吉田構内には、室町時代の屋敷跡が
本部2号館の調査で確認されています。その調査とともに、この地域における中世から近世にかけての集落の構造を解明する上で非常に貴重な資料を得ることができた調査区と言えます。